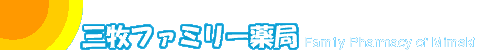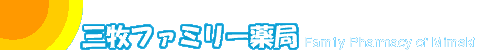| 丂傾儔價僲僉僔儔儞偼暷峟傪嵽椏偵奐敪偝傟偨婡擻惈怘昳偱丄偙傟傑偱偺尋媶偐傜俶俲嵶朎傪晩妶壔偡傞嶌梡傪帩偭偰偄傞偙偲偑柧傜偐偵側偭偰偄傞丅俶俲嵶朎偼娻嵶朎傗僂僀儖僗姶愼嵶朎側偳傪嶦偡摥偒傪帩偮偲偲傕偵丄僒僀僩僇僀儞傪暘斿偟偰柶塽斀墳傪挷愡偡傞婡擻傪帩偭偰偍傝丄偙偲偵庮釃柶塽偵偍偄偰偼廳梫側栶妱傪扴偭偰偄傞丅僑乕僫儉巵偐傜偼偦偆偟偨俶俲嵶朎晩妶壔偺偳偺傛偆側揰偵傾儔價僲僉僔儔儞偑摥偄偰偄傞偐偵偮偄偰専摙偟偨惉愌偑曬崘偝傟偨丅
丂俶俲嵶朎偑偳偺傛偆偵昗揑傪擣幆偡傞偺偐丄傑偨偳偺傛偆側婡峔偱嵶朎彎奞傪婲偙偡偺偐偼丄偙偙悢擭偺尋媶偱偐側傝柧傜偐偵側偭偰偒偨丅偦偺側偐偺堦偮偺僩僺僢僋僗偼丄俶俲嵶朎偺偁傞傕偺偼昗揑嵶朎忋偺MHC僋儔僗嘥暘巕傪擣幆偟丄偙偺擣幆偑偱偒側偔側傞偲昗揑嵶朎攋夡傪堷偒婲偙偡偙偲偑暘偭偰偒偨偙偲丅廬棃偼丄俶俲嵶朎偑MHC偺堎側傞僂僀儖僗姶愼嵶朎傗娻嵶朎傓傪傕彎奞偱偒傞偙偲偐傜丄MHC旕峉懇惈偺嵶朎彎奞惈傪帩偮偲偝傟偰偄偨偑丄幚偼MHC暘巕偑俶俲嵶朎偺昗揑擣幆偵廳梫側摥偒傪偟偰偄傞偙偲偑柧傜偐偵側偭偰偄傞丅
丂NK嵶朎彎奞惈偼丄彎奞傪懀恑偡傞惓偺僔僌僫儖偲梷惂偡傞晧偺僔僌僫儖偲偺僶儔儞僗偵傛偭偰挷愡偝傟偰偄傞偲峫偊傜傟偰偍傝丄偦傟偧傟偺僔僌僫儖偼昗揑嵶朎忋偺儕僈儞僪暘巕傪擣幆偡傞俶俲儗僙僾僞乕偑揱払偟偰偄傞丅偙偺偆偪梷惂僔僌僫儖傪弌偡儗僙僾僞乕堚揱巕偵偮偄偰偼夝柧偑恑傒丄KIR偲屇偽傟傞儗僙僾僞乕僼傽儈儕乕偑摨掕偝傟偰偄傞丅偦偺梷惂婡峔偲偟偰偼丄KIR偑昗揑嵶朎忋偺帺屓MHC僋儔僗嘥峈尨偺HLA亅俙丆俛丆俠暘巕偲寢崌偡傞偲丄梷惂僔僌僫儖偑揱払偝傟丄俶俲嵶朎偼昗揑傪嶦偝側偄丅偦傟偑帺屓偺惓忢嵶朎傪彎奞偟側偄巇慻傒偲側偭偰偄傞丅
丂偟偐偟丄傕偟KIR偑憡庤偺嵶朎傪擣幆偱偒側偄偲丄梷惂僔僌僫儖偑弌偢偵惓偺僔僌僫儖偑偦偺傑傑揱払偝傟丄俶俲嵶朎偼昗揑嵶朎傪攋夡偡傞偲偝傟偰偄傞丅娻嵶朎偑俿嵶朎側偳偺柶塽婡峔偐傜摝傟傞堦偮偺僔僗僥儉偲偟偰丄MHC偺敪尰掅壓偑抦傜傟偰偄傞偑丄俶俲嵶朎偺応崌偵偼MHC傪擣幆偱偒側偄偲惓偺僔僌僫儖偑摦偔偙偲偐傜丄俿朎嵶宯偱擣幆偱偒側偄娻嵶朎傪傕攋夡偡傞偙偲偑偱偒傞丅
丂堦曽丄俶俲嵶朎彎奞婡峔偲偟偰偼丄俶俲嵶朎偺嵶朎幙拞偵懚嵼偡傞梓棻偑丄昗揑嵶朎偲偟偨寢崌偟偨嵺偵惗偠傞嵶朎娫偺寗娫偵曻弌偝傟丄偦傟偵傛偭偰嵶朎攋夡偑婲傞偙偲偑抦傜傟偰偄傞丅偙偺梓棻偺側偐偵偼70k俢a偺摐抈敀偱偁傞僷乕僼僅儕儞暘巕偑偁傝丄偦傟偑昗揑偲側偭偨嵶朎枌偵岴傪奐偗丄嵶朎撪傊偺奜塼偺棳擖側偳偑婲偭偰丄昗揑嵶朎偑巰偸偲偝傟偰偄傞丅傑偨丄梓棻偵偼僙儕儞僾儘僥傾乕僛暘巕孮偑娷傑傟偰偍傝丄僷乕僼僅儕儞偑奐偗偨岴偐傜嵶朎撪偵棳擖偟偰丄DNA傪抐曅壔偟傾億僩乕僔僗傪婲偙偡偙偲傕暘偭偰偒偰偄傞丅
丂僑乕僫儉巵偑偦偆偟偨俶俲嵶朎嶌梡偵懳偡傞傾儔價僲僉僔儔儞偺岠壥傪専摙偟偨偲偙傠偱偼丄昗揑嵶朎傊偺俶俲嵶朎偺寢崌擻偑丄傾儔價僲僉僔儔儞搳梌偵傛偭偰柧傜偐偵岦忋偡傞偙偲偑擣傔傜傟偰偄傞丅偝傜偵丄娻嵶朎側偳偵傛偭偰婲偒偨俶俲嵶朎撪梓棻偺尭彮偵懳偟偰傕丄傾儔價僲僉僔儔儞偼嵞梓棻壔傪懀偟丄彎奞惈傪傕偭偨俶俲嵶朎偵偡傞摥偒傪傕偭偰偄傞偙偲偑撍偒巭傔傜傟偰偄傞丅偮傑傝丄傾儔價僲僉僔儔儞偼俶俲嵶朎偑娻嵶朎側偳傪擣幆偡傞擻椡傪崅傔傞偲摨帪偵丄昗揑嵶朎傪懪偪搢偡偨傔偺晲婍傕廩幚偝偣偨偙偲偵側傞丅
丂傑偨丄傾儔價僲僉僔儔儞偼俶俲嵶朎偺妶惈壔偽偐傝偱側偔丄俿嵶朎傗俛嵶朎側偳偺柶塽宯慡懱傪晩妶壔偡傞偙偲傕丄僑乕僫儉巵傜偼尒弌偟偰偄傞丅摿偵嶻惗偑崅傑傞偺偼俬俥俶乮僀儞僞乕僼僃儘儞乯傗俿俶俥乮庮釃夡巰場巕乯偱丄俶俲嵶朎偐傜嶻惗偝傟偨IFN亅兞偑枹暘壔偺俿嵶朎傪嵶朎惈柶塽宯偺俿嵶朎乮俿倛倢乯傊偲暘壔偝偣偨傝丄俿俶俥偑峈庮釃惈偵摥偔側偳偟偰丄柶塽宯慡懱偑晩妶壔偝傟傞偙偲偑柧傜偐偵側偭偰偒偰偄傞丅
丂偄偢傟偵偟偰傕丄峈庮釃嶌梡傪傕偮柶塽宯偱戝偒側栶妱傪壥偨偟偰偄傞偺偼俶俲嵶朎偱丄偙傟傑偱偵傕俶俲嵶朎偺妶惈壔傪慱偭偨柶塽椕朄偑庢傝擖傟傜傟偰偒偨丅偦偺戙昞揑側傕偺偲偟偰傛偔抦傜傟偰偄傞偺偑俬俴亅俀偺搳梌偱丄俶俲嵶朎偼俬俴亅俀偺巋寖偱憹怋妶惈壔偝傟丄俴俙俲妶惈傪帵偡傛偆偵側傞丅
丂偨偩丄崅擹搙偺俬俴亅俀搳梌偺応崌偱偼暃嶌梡傕嫮偔丄偙傟傑偱偺椪彴専摙偱偼廫暘側惉壥偼摼傜傟偰偄側偄丅偦偺偨傔丄掞梡検偱傕俬俴亅俀偑峈娻嶌梡傪敪婗偡傞傛偆側暪梡椕朄側偳偺奐敪偑懸偨傟偰偄傞丅僑乕僫儉巵偼偦偆偟偨揰偵拝栚偟偰丄傾儔價僲僉僔儔儞偲偺暪梡椕朄偵偮偄偰傕専摙傪峴偭偨丅
丂幚尡偼僸僩枛徚寣俿儕儞僷媴傪梡偄丄傾儔價僲僉僔儔儞扨撈丄俬俴亅俀扨撈丄傾儔價僲僉僔儔儞偲俬俴亅俀偺暪梡偺俁孮偵暘偗偰丄俶俲嵶朎妶惈偺曄摦偵偮偄偰挷傋傜傟偨丅偦偺寢壥偱偼丄傾儔價僲僉僔儔儞扨撈偱偼138.6%丄俬俴亅俀扨撈偱偼179.5%丄偲俶俲嵶朎偺妶惈偑摼傜傟偨偑丄椉幰傪暪梡偡傞偲僐儞僩儘乕儖偵懳偟偰332.7%偲崅偄憡忔岠壥偑摼傜傟傞偙偲偑敾柧偟偰偄傞丅
丂側偤丄偦偆偟偨憡忔岠壥偑摼傜傟傞偺偐偵偮偄偰偺儊僇僯僘儉偼丄尰嵼偺偲偙傠廫暘偵偼夝柧偝傟偰偄側偄偑丄僑乕僫儉巵偼乽傾儔價僲僉僔儔儞偺俿俶俥亅兛嶻惗嶌梡偑戝偒偔塭嬁偟偰偄傞傕偺偲峫偊偰偄傞丅乿偲曬崘偟偨丅幚嵺丄僑乕僫儉巵傜偑寬忢旐尡幰20柤偺枛徚寣儕儞僷媴傪巊偭偰専摙偟偨偲偙傠偱偼丄僐儞僩儘乕儖偑195pg乛ml亇102偵懳偟偰丄
俬俴亅俀張棟孮偱偼216pg乛ml偲丄俿俶俥亅兛検偵壗偺曄壔傕尒傜傟側偐偭偨偺偵懳偟偰丄傾儔價僲僉僔儔儞張棟孮偱偼5773pg乛ml亇2653偲丄俿俶俥亅兛偑懡検偵嶻惗偝傟傞偙偲偑擣傔傜傟偰偄傞丅傑偨丄椉幰傪暪梡偟偨寢壥偱偼8127pg乛ml亇2578偲偝傜偵嶻惗偑憹壛偡傞偙偲偑撍偒巭傔傜傟偰偍傝丄俬俴亅俀偺搳梌検傪掅偔偟偰傕俶俲嵶朎偑妶惈壔偝傟傞偙偲偑柧傜偐偵側偭偰偄傞丅崱屻丄椪彴墳梡側偳偵偮偄偰専摙偝傟傞偙偲偵側偭偰偄傞偺偑丄傾儔價僲僉僔儔儞偺暪梡偵傛偭偰丄掅梡検偺俬俴亅俀偱俶俲嵶朎偺妶惈壔偑摼傜傟傞揰偱偼丄怴偨側揥奐偑婜懸偝傟偦偆偩丅
|